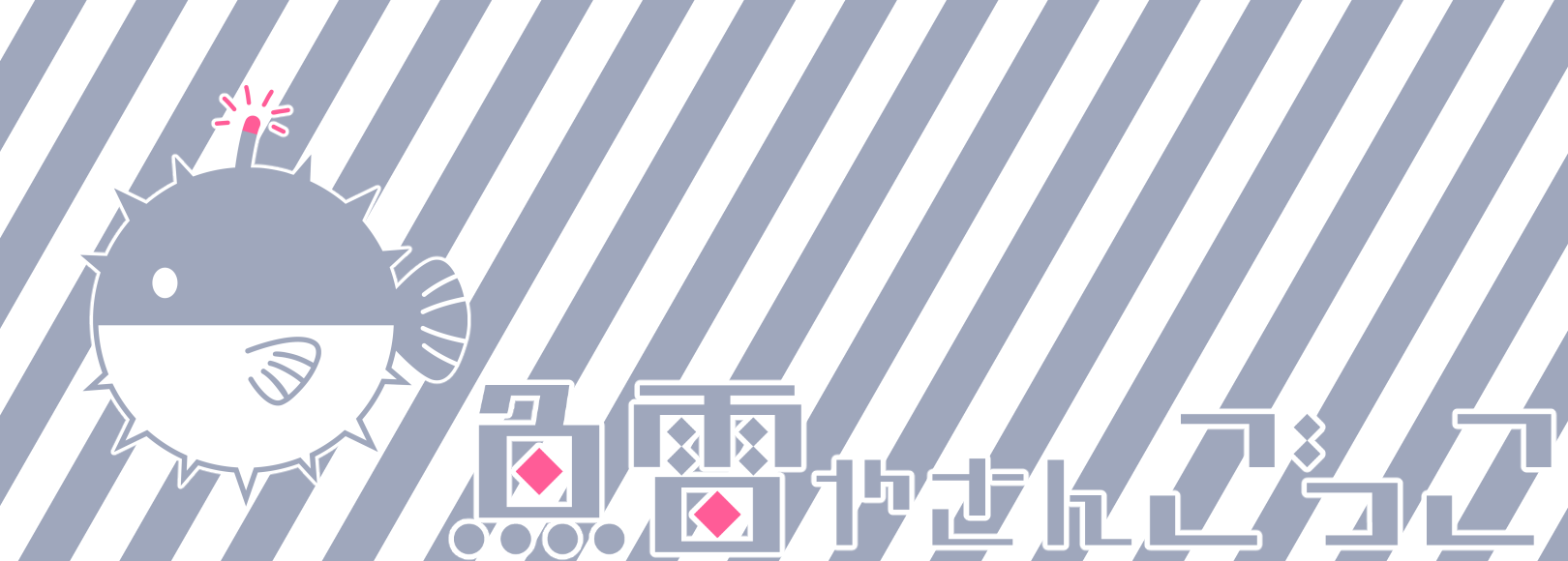クリスマスのあとは年越しだ。年末年始がダッシュで迫ってくるこの時期は、さすがにイベント盛り込みすぎだろうと呆れてしまう人もいるだろう。それはイブキと名乗る男もそうだった。
チェーン飾りのついたバンスクリップで髪をまとめた彼は、部屋に散らばる本を動かして本棚に戻していく。まるで魔法のように勝手に本が動いて本棚に戻っていく。次々に本棚に戻る本たちのおかげで、あっという間にフローリングが見え始める。
――そう、本が勝手に本棚に戻るのだ。あり得ない光景をあり得るものにした男は、なんでもないことのように、清掃業者からレンタルしているモップに指先を向けて、何事か呟く。すると、モップが今度は自主的に動き出す。するすると動いて、床を隅々まで拭き上げていく。
「今年は暖冬らしいし、ダウンの上着はいらんかぁ」
明るい茶色の目を細めて、彼はボタニカルな模様の入ったシャツの上から、ウールの無地のコートを羽織る。赤いソールが目立つピンヒールを履いた彼は、そのまま勝手気ままに動くモップを放ってそとに出る。
玄関を施錠すると、アパートを背に歩き出した彼は、大学もやってないしなー、とぼやきながら駅前に向かうバス停に向かう。ふんふんと鼻歌を歌いながらバス停に向かえば、そこには一人の男が立っていた。
ひょろりと背が高く――それでもピンヒールを履いているイブキのほうが少しばかり背が高い男だった。紫がかった黒い髪。前髪はやや重ために切りそろえられ、後ろ髪も首を隠す程度の長さだ。長いまつげに縁取られた切れ長の目は、黒がかった灰色の目だ。
顔のパーツは左右平等で、美人や美男子という言葉がしっくりくる男だ。ぱっちりとした目にぷっくりとした唇をした、女顔のイブキとは違う、男性に少しばかりステータスを振り分けた中性的な美男子だった。
千種川雅貴。それがバス停に立っている男の名前だった。
ぼんやりと立っている千種川を見つけたイブキは、おおーい、と手を振りながら声を掛ける。声に反応した千種川は、イブキの方を見ると小さく会釈をする。
「こんにちは」
「ちわぁ。千種川くんも駅にいくんか?」
「はい。書店に注文していた書籍が届いたそうなので、引き取りに行きます」
「ええね。難しそうな本なんやろなあ」
「試しに読みますか」
「うんにゃ。遠慮しておくよ」
イブキくんは難しい本は睡眠導入にしかならんからなあ。
そうからからと笑うイブキに、そうですか、と千種川は返答をする。それでな、と会話を続けるイブキに、千種川はちら、と彼を見てから視線を道路に戻す。
「さっきなあ、大掃除しててん。あかんなあ、漫画本はちゃんと棚にしまわんと、何巻まで買ったかわからんくなるわ」
「それはそうでしょうね。ナンバリングを確認できなければ、続編を買うのに支障が出るでしょう」
「ほんにそうなんよ。ぜーんぶ戻してな、床を拭き上げたら、もー腹減ってしゃああらへんのよ」
「なるほど。飲食店に向かうと」
「そういうことやね。ほら、この辺お店あらへんやん?」
「少ないのは事実ですね」
「無駄遣いが減るんはありがたいんやけど、コンビニすら遠いんがなあ」
「そこまでコンビニは遠いでしょうか」
「駅までいかなあらへんのは遠いんよ、イブキくんにとってはな」
肉も食べたいしピザもええかなあ、と笑う彼に評判のいいイタリアンレストランを姉から教えてもらったと千種川が提案すると、ファミレスの安いピザでええのよ、とイブキは色を付けた爪先を持つ手をひらひらと振りながら遠慮する。
そうですか、と感慨もない千種川に、一緒に食べに行くか、とイブキは頭の良いことを思いついた、と言わんばかりに提案をする。
「千種川くんも一緒にどうやろ。割り勘やけど」
「ありがたい申し出ですが、昼食は自宅で食べましたので」
「あーらら残念。フラれてもーたなあ」
くっくっ、と笑いながらイブキは定刻通りに滑り込んできたバスに乗る。千種川も同じように乗るが、イブキはバスの運転手のすぐ後ろの座席に座るが、千種川は後部座席に歩いていく。
自分の横を通り過ぎる千種川に、イブキはひらひら、と手を振ってみるが、千種川は一瞥すらしていないのか無反応で通り過ぎていく。それすら面白いのか、イブキはもう一度喉を鳴らして小さく笑うのだった。