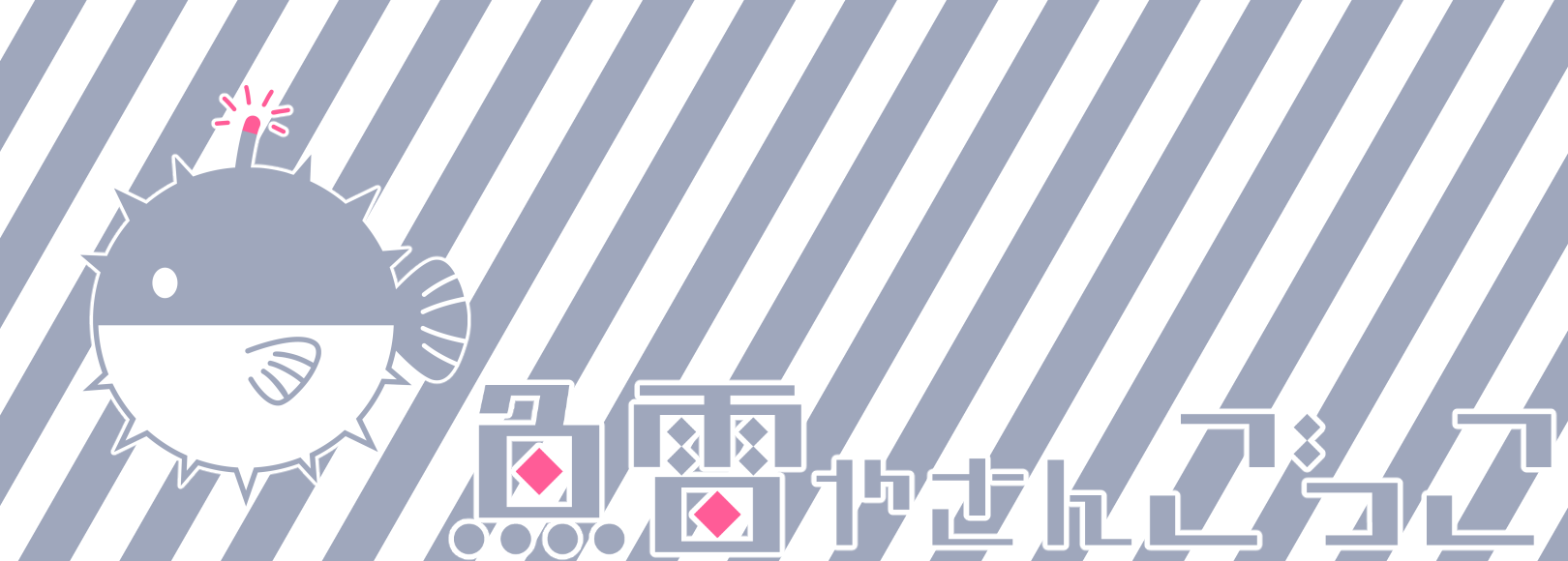十月に入り、急速に気温が冷えてくる。この間まで厳しかった――夏と変わらない残暑はなんだったのか、と思いながら、優はパーカーのポケットに手を入れる。隣を歩く男も、流石に冷えてきたのか長袖のロングTシャツを着ていた。
自販機かコンビニで温かい飲み物が欲しくなるのももう時期だな、と優が考えていると、千種川が足を止める。どうしたのか、と優が声をかける前に、彼が口を開く。
「ハロウィンですね」
街中にあるショップがオレンジ色と紫色に彩られ、ハッピーハロウィーンと書かれたポップを提示しはじめた頃、雑貨屋の前で足を止めた千種川がそう口を開いた。
そうだねえ、と優も足を止めて雑貨屋の大きな窓を見る。そこに並んでいるのは、大きめの藤でできた底の浅いカゴに入ったお菓子の袋。ラッピングされたマシュマロやクッキー、チョコレートたちが飾られており、その周辺にかわいらしくデフォルメされたおばけたちと、飾り物のイミテーションだろうジャック・オー・ランタンが並んでいる。
すっかりハロウィーンに染まっている店先は、藤のカゴの下にオレンジ色の布が敷かれている。ハッピーハロウィーンと書かれたポップまでご丁寧に添えられている。
「すっかり定着したって感じ」
「面白いものですね。文化が伝播し、姿を変えていくのですから」
「一番面白い姿の変わり様はバレンタインだと思うけど……まあ、たしかに。これだって、移民達が広めていったんだっけ」
「そうですね。アメリカ大陸に移住したスコットランドおよびアイルランドの人々からはじまり、アメリカの主流社会になじむと東海岸から西海岸へ。そして、世界各国で軍事的・経済的に活動する彼らにより世界中に広まっていったと聞いています」
「まあ、日本人からすれば子どもはお菓子がもらえる日、ってぐらいだけどね」
あたしはそこまで甘い物好きじゃないから、もらっても困るけど。
そう笑った優に、そうですね、と千種川も頷く。もとは古代ケルトの一年の終わりの日だそうですし、と続いた彼の言葉に、優はへえ、と相づちを打つ。
駅に向かって歩きながら、二人は古のハロウィーン、古代ケルトの話をする。
「一年の終わりなんだ、十月三一日が」
「ええ。夏の終わりを意味するサウィン祭が起源だと考えられ、現世と来世を分ける境界が弱まる時。そして、死者の魂が家族のもとへ戻ってくる日だとも言われています。このあたりは、どちらかと言えばお盆の考え方に近いでしょうか」
「盆と正月が一緒に来た感じの日だ、ってのは分かったわ」
「死者の魂とともに悪霊も一緒にやってくると考えられ、その悪霊に人間だと気づかれないように、火を焚いたり仮面を着けたりして身を守った……この風習が、ハロウィンの代表的な習慣である仮装の起源となったと言われていますね」
「ふうん。まあ、今じゃその辺はあまり深く考えられること無く、愉快なコスプレショーもどきみたいなことになってる、ってワケね」
「そうですね。ハロウィンをあげるなら、同様の祭りとしてメキシコの死者の日もあげられますね」
「死者の日」
ド直球なネーミングね……と苦笑しながら優はスマートフォンを開くと、インターネットブラウザーを起動させる。検索欄に死者の日、と入力して画面を開く。少しだけ読み込みがあって、表示されたのは鮮やかなビビッドカラーのドクロたちだったものだから、ちょっとだけぎょっとしてから、よくよく見ればかわいいわね、とまじまじとスマートフォンの画面を眺める。
「前夜祭がハロウィーンと同じ十月三一日ですが、子どもの魂が帰る日が翌日の十一月一日、大人の魂はさらにその翌日である十一月二日とされています」
「子どもと大人とで戻ってくる日が違うんだ。面白いわね」
「そうかもしれませんね。彼らが戻ってくる日に合わせて、オフレンダと呼ばれるマリーゴールドやケイトウの花、フルーツなどで飾り付けられた祭壇を用意するとか。やはりお盆に通じるものがありますね」
「どこでも死者のお祭りってなると、花を用意するもんなのかもね」
「そうなのでしょうね。彼らにとって、死者とともに明るく楽しいひと時を過ごし、祭りを終えた後には死者が満足して死者の国へと帰れるように祈る日ですから、墓前で賑やかに食事をしたり、音楽を奏でたりするそうです。こちらは沖縄に見られる光景でしょうか」
「ああ、それ、聞いたことあるな……シーミー、だっけ」
「そうですね。その行事を広めたのはコメディアンだとか……脱線しましたが、メキシコにも死者の日に食べる菓子パンがあるそうでして」
「菓子パンって時点で甘そうね……」
「十字架をかたどった生地に砂糖をまぶしたパン・デ・ムエルトといいます。調べた限りですが、オレンジの風味がするそうですよ」
「へえ、オレンジの風味がするなら、食べやすそうだわね」
ちょっと気になるし、作れるものなのかしら。スマートフォンを仕舞って、腕を組んで考える優に、以前公共放送でレシピが紹介されていましたね、と千種川が思い出すようなそぶりをしながら言う。それならネットで調べるわ、と優は頷く。
駅にたどり着くと、二人は別れる。優は自宅へ向かう電車に乗り込みながら、スマートフォンでパン・デ・ムエルトのレシピを検索する。上位に表示された公共放送のレシピページを開く。上白糖とコンデンスミルクの文字に、うわ、と眉を潜ませ、さらに下段に焼くときにグラニュー糖という文字を見た優は頭を抱えたくなる。甘すぎるのではないか。
「これでもか、ってくらい甘味を足して行くわね……舌がバカになるんじゃないの、流石に……」
焼けばそこまで甘くはないのだろうか、と少しだけ考えてみて、やっぱり甘いのではないか、と考えを戻す。そんなことをしているうちに、降りるべき駅に電車は停まり、優は車両をあとにする。
改札口でICカードをタッチして、改札を抜ける。その間もちら、とスマートフォンを見ては、レシピに記載のある材料が果たして家にあるのか考えを巡らせる。とはいえ、ほとんどキッチンに入らない優では、どこになにがあるのか知らないことの方が多くて、すぐに辞めたのだが。
スマートフォンを仕舞いながら、駅から自宅方面に向かって歩く。レシピの分量には八〇グラムが六つ分とあった。パン一つあたりの平均のグラム数など知らないが、まあ一般的な大きさのパンを作るのなら、そのぐらいだろう。
「そもそも、アニスリキュールとか、アニスパウダーって普通のスーパーに売ってるのかしら」
売っているか確認して、近くのスーパーで取扱があるのなら、パンを作るのも吝かではない。そう考えて、優は自宅に向かっていた足の先を、近所のスーパーマーケットに向け直すのだった。