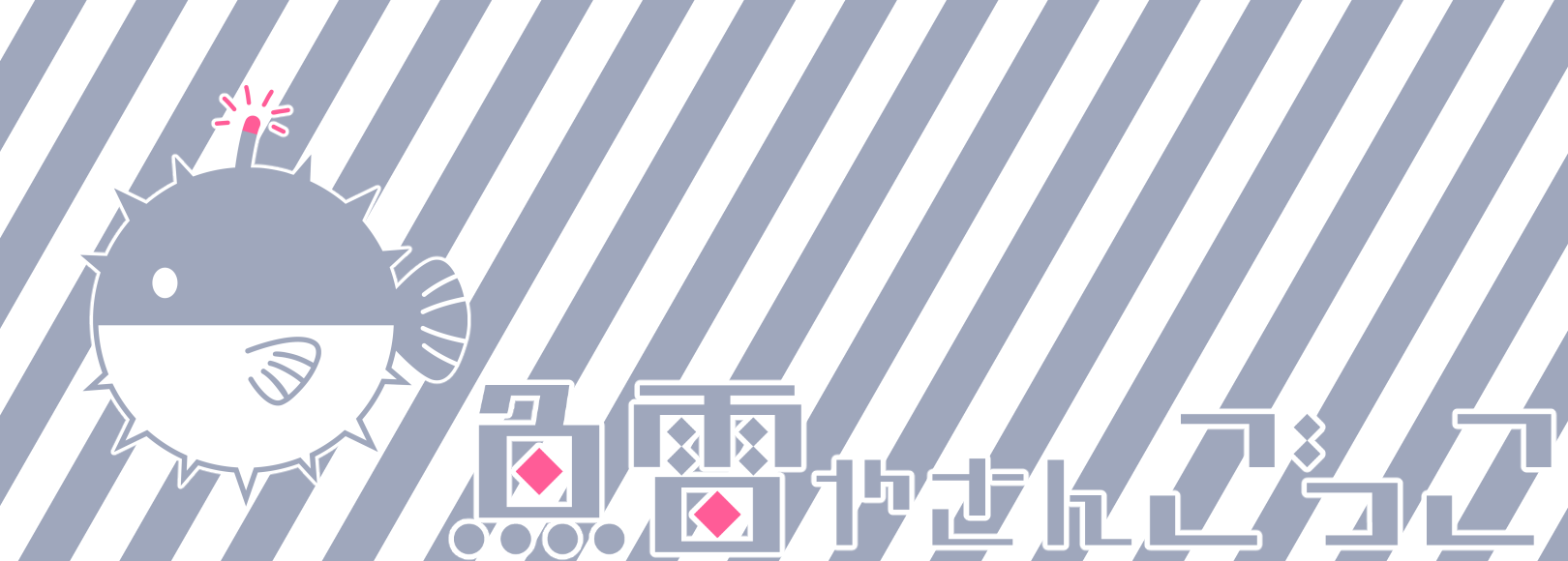斜向かいに座る男は美男子だ。美男子、という言葉ですら足りないほどに顔がいい。そして、イケメンという言葉ではチープすぎて物足りない。あらゆるイケメンアイドルや俳優を寄せ集めて、AIに学習させて描いたらこんな顔が出力されるんだと思わせる顔の良さだ。
そんな顔のいい男は、斜向かいに座ってパスタを食べている。咀嚼の口の動きも目立たず、音も立てない。カトラリーが触れ合う音すら聞こえない。器用なものである。
……じっ、と見ていたからだろうか。向かいに座る男がこちらを見る。うっ、と思わずたじろぐ。相変わらず表情のない、気味の悪い目をしている。ガラス玉だってもう少しマシな目をしている。
「……なにか、僕の顔についていますか?」
「あー……いや、なんでも」
「そうですか」
会話が途切れる。そもそも、向こうが繋げるつもりもない会話だ。反応があっただけまだマシかもしれない。
やりにくさを感じているのはこちらだけで、相手は興味もなさそうにパスタに視線を向け直している。くるり、とフォークで巻き取り、口に運ぶ。一連の仕草すら美しいのだから、得な男は存在するものだ。
斜向かいの美男子を無視して、あつあつのカツ丼に箸をつける。よく味の染みた衣を、包んでいる肉ごと噛む。歯で細切れにするたびに、濃いめに付けられた味が口の中にいっぱいに広がっていく。とろとろの卵とかきこんでいると、隣に見知った顔の男が座ってくる。同じサークルの男だ。
よう、と挨拶して、混んでてさ、と別に気にしていないのに事情を説明してくれる。確かに昼時の食堂は混み合っている。それはまあ、いつものことだ。
チャーハンとラーメンのセットを持ち込んだ彼は、そういやさあ、と口を開く。そういえば、この男は口を開けば下ネタしか出てこない男だったはずだ。公共の場で率先して喋らせるな、とは先輩の教えだ。それを思い出した俺は、口を閉じさせようとしたが、一歩遅かった。
「彼女がさー、ヤらせてくれねえの。連れねえよな」
「お前なあ……公共の場所でそういう話はやめろよ……周りに迷惑だろ……」
「はあ? 誰も聞いちゃいねえって。それとも、なんだよ。ドーテーくんには刺激が強すぎたかあ?」
「はあ……お前、そのうち誰かに刺されるぞ」
「んなことねえって。なあなあ、千種川もそう思うよな?」
馴れ馴れしげに美男子に声をかけるあたり、この男のコミュニケーション能力が高いのか、それとも単純に空気が読めないだけなのか――おそらく後者だが、千種川雅貴に声をかけている。
話しかけられた千種川は、紙ナプキンで口元に僅かについた汚れを拭っているところだった。彼は二度瞬きをしたあとに、性行為の話は不特定多数がいる場所で行うのはマナー違反だと思っていましたが違いましたか、と真顔で尋ねてくる。お前はまともな常識を持っていたんだな。
「ですが、貴方が興味があるなら会話を続けますしょう」
「あ……乗るのね……」
「てか、千種川って女入れ食い状態だったらしいじゃん? 急に辞めたって聞いてびっくりしたんだよな」
「以前までが可笑しかったのです。そもそも、彼の破滅的な女性関係は褒められたものではないですから」
(……ん?)
千種川は不思議な言い回しをした。自分のことを彼、と呼んだのだ。まるで――今と昔で人格が違うような発言だ。
それに違和感を覚えているのは俺だけのようで、隣の下卑た男はいい子ちゃんかよ、と毒付いている。
「てか、千種川って女相手に勃つわけ?」
「勃起状態ですか? 可能ですが」
「マジで!? お前、性欲あんのかよ! ちょっとみてーわ」
「おまっ、声でけえって」
「相手誰よ。たまーに、胸と尻がすげえ女と歩いてるって聞くけどよ」
「胸と尻……ああ、優のことですね。彼女とは友好的な交友関係を築いています」
「へえ、よかったら紹介してくれよ。いいだろ?」
「構いませんが、彼女の知性と貴方の知性では隔絶しすぎているから、話が通じないと思いますよ」
「千種川……こいつな、単にヤりてえってだけだから気にしなくていいぞ……」
「そうでしたか。それは失礼しました。対話がしたいものだとばかり思っていました」
「ヤりたい盛りみたいな言い方すんなよな。男なら女と一つになりたいもんじゃねえの? この時期なんてさ」
「それはねーわ」
「ないですね。そもそも、欲求の処理に他人は必要すらない」
最近では処理用のグッズも多数ありますから、それを利用すればいいですから。
水を煽った千種川は、講義がありますので、と空の皿を乗せたトレイを持って立ち上がる。姿勢良くスタスタと歩き去っていく彼に続くように、俺も空の皿をトレイに乗せて返却口に向かう。
先程までのやり取りは、賑やかな食堂の声にかき消えていたらいい。そう思いつつも、どうにも他人の視線が気になって足早になるのを止められなかった。