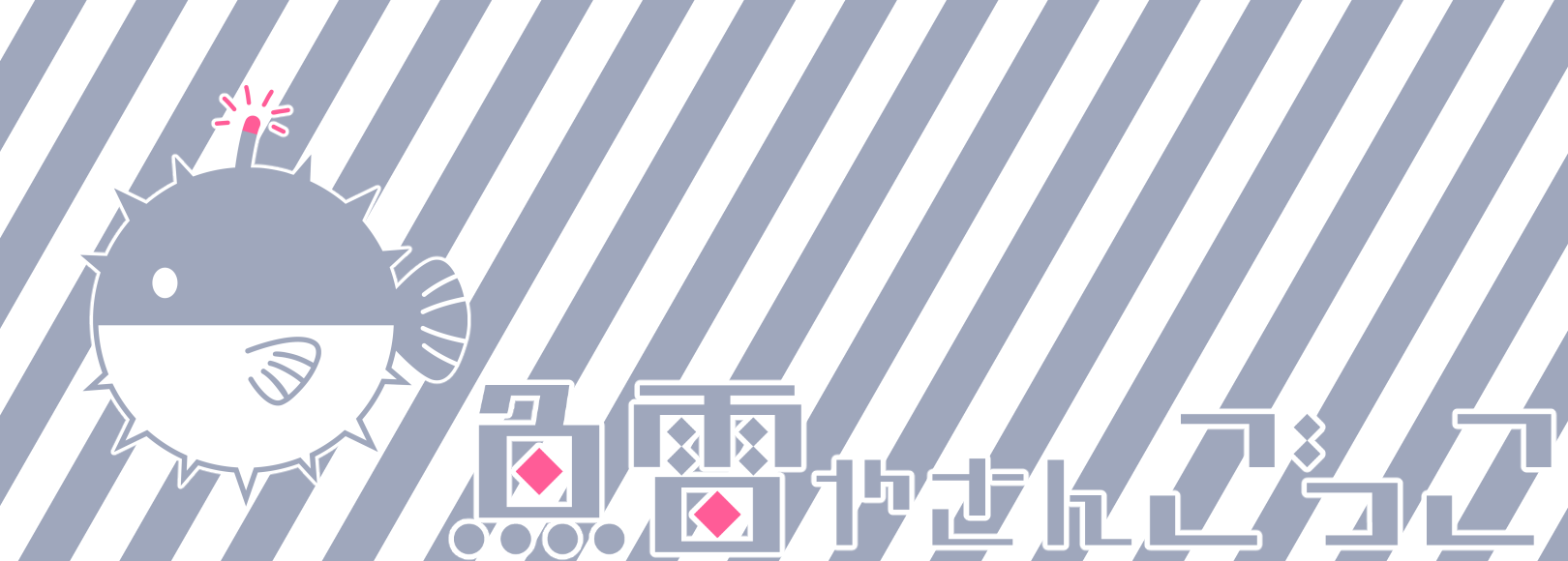「クリスマスじゃん」
「ええ、キリスト降誕祭と聞きましたので。欧米では一般に家族で過ごすものと聞いておりますが、日本では恋人と過ごすと聞きました。ぼくと優はそのような関係性ではありませんが、そのように誤解されることも多々ありますから、ぼくなりに乗っかってみる、ということをしてみました」
「あんたってたまに面白いこと考えるよね……まあ、いいけど。え、てかなにこれ。めちゃくちゃおいしそうじゃん。砕いたナッツとか、家で出るケーキにはないし」
「大学の学生に聞きました。クリスマスに仲の良い相手と食べるなら、どのようなケーキがいいのか、と」
滔々と語る千種川に、優はそれを聞いた大学生の顔を思い浮かべる。とはいえ、顔など知らないからへのへのもへじの顔であるが、その顔が困惑に歪むのが目に見えるようだった。なにせ、その質問だけなら、恋人と二人で過ごすような質問だからだ。
目に見えるようなそれに、くっくっ、と喉を鳴らして笑う優。そんな彼女を見て、無表情ながら首を傾げる千種川だが、なにかまずいことを言ったのか、と尋ねれば恋人だと勘違いされてるよ、と返す。
「それ、絶対勘違いされてるわ」
「そうでしたか。きみのことを仲のいい友人だと認識しているのですが、難しいですね。正しく事実を伝達するということは」
「年下の女の友人、って言ったりしたんでしょ。あとは二人で食べるとか」
「見てきたような質問ですね。その通りです。事実ですから、問題はないでしょう」
「あーね、大抵の人間って、前にも言ったけど男女が二人で食事をするっての、恋人かそれに準するものだと思われるの」
「ふむ。恋人の定義が曖昧ですが、性行為もしますから、ぼくたちもそれに当たるのでしょうか?」
「どうだろ。結婚したいとか思わないし、好きか嫌いかと言われたら好きだけど、恋愛感情があるかと言われたらないかな」
「なるほど。恋愛感情とは、以前言っていた「ドキドキする」や「近づきたい」と思う感情ですね。確かにその定義で言えば、ぼくらの間には恋愛はあり得ません。性行為も行う男女の友人という括りが正解でしょう」
「ま、そういうのはなかなか理解してもらえないもんだし。あと人前で明け透けに性行為するって言わないようにね」
流石にちょっと恥ずかしいから。
そう言いながら、優はファッションホテルのテーブルに広げた箱の中を見る。その中には小さくも見栄え良く飾り付けられたケーキが二つ並んでいる。
「それでこんなインスタ映えしそうなケーキ買ってきたんだ」
「ええ。優は甘いものが好きですから、店員に尋ねたところ、こちらのキャラメルナッツがいいと言われたものですから。ベリーのものも甘酸っぱくてしつこくないからおすすめ、だとも」
「ふーん。……これ、両方ともあたしに?」
「ええ。ぼくは嗜好品の類はいらないので」
「ふーん……じゃあ半分こね」
「半分こ、ですか」
「二つも食べたら太りそうだし」
「なるほど。カロリーはこれから消費しますが」
「食べてすぐえっちはしたくないんだけど」
「そうでしたか。では、今日はしないということですか?」
「あー、ん。そだね。まあ、そんな日があってもいいでしょ」
「きみがそう言うのなら、ぼくはそれに従うだけですから」
おまけとしてケーキ屋側が付けてくれた使い捨てフォークのパッケージを破ると、優は千種川にフォークを渡す。受け取った彼は、すっ、とフォークを入れると綺麗に寸分の狂いもなく二つに分ける。
二つのケーキを四つに分けると、こっちもらうわ、と優は切り分けられたケーキの片方を口に入れる。キャラメルの甘さとダークチョコレートの苦さに、小さく砕かれたナッツの食感がなんとも上品な味に、そこそこ値段が張る店に行ってきたな、と優は考える。考えるだけで指摘はしない。なぜなら、クリスマスとは無縁な関係性と空気であっても、頂き物に違いないからだ。
「おいしいじゃん」
「そうですね」
「たまにはいいね。この店さ、イートインあるわけ?」
「……ありましたね、そういえば。気に入ったのなら、今度は一緒に行きましょうか」
「ん。そうしよ」