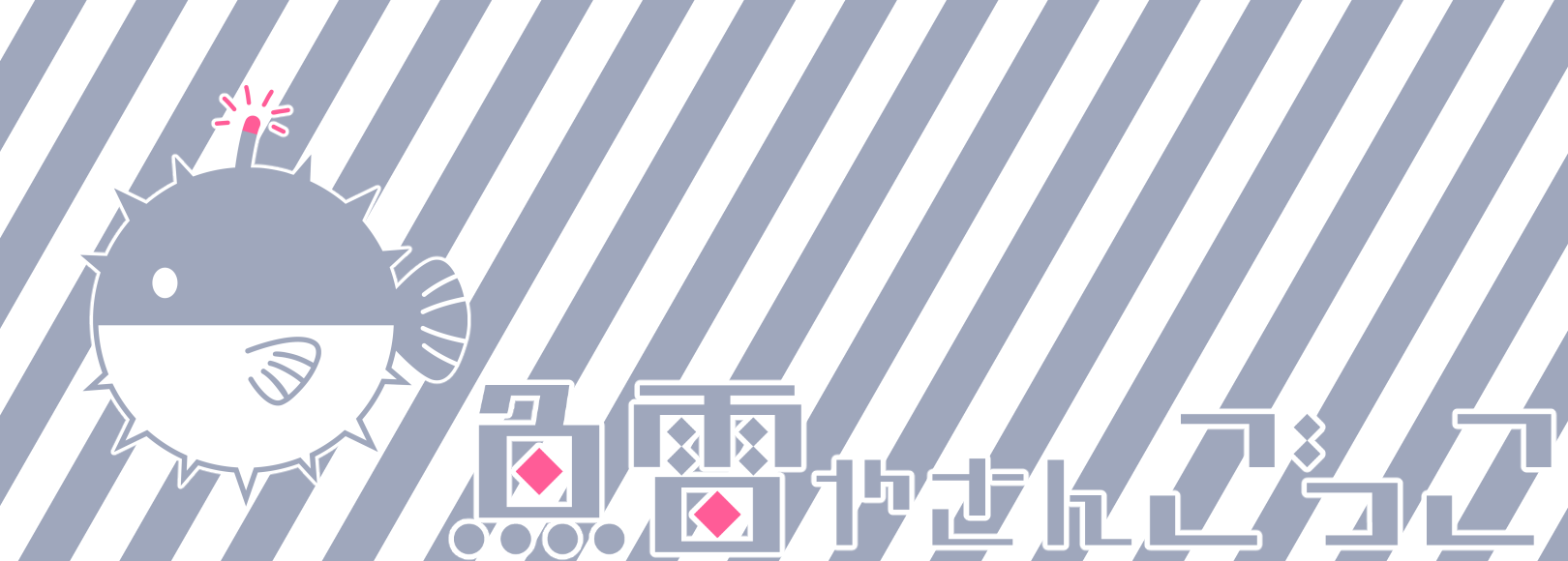ほかほかと湯気を立てている中華まんを、あち、と言いながら優は掴む。敷き紙を剥がして中華まんを二つに割る――中は肉まんのそれの片方を千種川に渡す。きょとん、としている彼に、あげる、と優は言う。首を傾げている彼に、ため息をつきながら優は手に押し付ける。押しつけられた千種川は、不思議そうな顔をしている。どうして肉まんを押しつけられたのか、さっぱり分かっていない顔だ。
「あげる」
「……それは優が購入したものでは?」
「ん。だからあげる。あたしが買ったものだから、別にいいでしょ?」
「君がそれでいいのなら、ぼくは構いませんが。半分にするなら、なぜ購入したんですか?」
「家に帰って、すぐにご飯が出るわけじゃないでしょ。でも、お腹は空いてる。それでも肉まん一つまんま食べたら、夕飯が全部入らないかもしれない……けれどお腹は空いてるから、苦渋の決断ってやつよ」
「なるほど。でしたら、この時間まで外出させてしまったのは、よくなかったですね」
「……別に、家にいてもやることないし」
外に出るのが嫌なわけじゃないわよ。
そう言った優は、あむ、と肉まんをかじる。実際、彼女の家は関係性が冷え込んでいるものだから、夕飯を残したところで何も言われないだろうが、せっかく作ってくれたものを堂々と残すほど、彼女の性格はひねくれても曲がっていない。
肉まんを半分にして、千種川におしつけた理由は分かったのだが、自宅に居たくないという理由までは分からない彼は、無表情ながら不思議そうな顔をしている。冷えないうちに肉まんを食べるように促されて、彼はもそもそと肉まんに口をつける。コンビニの保温器の中で温かさを維持されていたそれは、寒い屋外に出されてもまだ食べ頃の温度を維持している。
ゆるやかに冷えていく肉まんを腹に収めた二人だったが、ふと足を止める。信号機もない住宅街の舗装された道路で足を止めた二人は、ふと空を見上げる。上からはしんしんと小さな白い粒が降り注いでいた。耳が痛くなるほどの冷え込みだ。雪が降ってもおかしくはないだろう。
「あら、雪」
「この地方では初雪ですね」
「まあ確かに凄く冷え込むものね。雪ぐらい降ってもおかしくないか」
「ええ。積もるほどの寒さでも、地域でもありませんから、明日の通学には問題ないかと」
「それはそれで残念ね。まあ、雪が積もったぐらいで休みにはならないから、別にいっか」
「雪が積もって欲しかったのですか?」
優はそういう、雪が積もるという事態に喜びを見いだす性格はしていないと思っていましたが。
目を丸くして驚く千種川に、単純に交通機関が麻痺したら学校に行かなくてもいいからちょっと嬉しいだけよ、と理由を説明する優。その説明を聞いて、そういう喜び方もあるのですね、と千種川は頷く。
「世間的には、交通機関の麻痺は輸送や業務に支障が出るため、喜ばれないものですが、そういう事態を喜ぶのは優のような学生の特権なのかもしれませんね」
「そうね。子どもは雪が降って電車やバスが止まれば学校に行かなくていいって思うわね。もう少し幼い子どもなら、雪遊びができるから学校があろうがなかろうが喜ぶものだわ」
「ふむ。年齢による、ということですね。ある程度の年齢だと、学校に行くのが億劫だと感じるものだと聞いていますから、その年齢層が喜ぶと言うことでしょうか」
「まあ……中学高校あたりは嬉しいものなんじゃない?」
あたしだって、寒くて滑りそうになりながら学校に行くのはちょっと嫌だし。
優はブーツの底でアスファルトを踏みしめながら答える。革製のそれは、先日防水スプレーをかけなおしたとはいえ、長時間雪に当たっていいものではない。足早に帰路に就く彼女の半歩後ろを歩きながら千種川は、そういうものなのですね、と理解したように頷く。そして、そういえば、と言葉を紡ぐ。
「童謡に”犬は喜び庭駆け回り、猫はコタツで丸くなる”とありましたが、あれは事実でしょうか」
「どうだろ。うち、ペット飼ってないんだよね。でもSNSだとコタツで丸くなっている猫とかいるし、そんなもんじゃないの」
「ふむ。猫はコタツで丸くなるのですね。犬は庭を駆け回るのでしょうか」
「犬によるんじゃないの? 寒いのが平気な犬なら外に出たがるかも知れないけど、室内で飼っている犬なら案外コタツで丸くなっているんじゃない?」
「なるほど……童謡は事実も含まれている、という認識をしておいた方が良いのですね」
「まあ、あくまで歌だけどね……ある程度はその時代を映しているものだし、案外作られた時代では犬はだいたい庭を駆け回っていたりしたんじゃないの?」
あくまでもあたしの想像だけどさ。
そう言いながら、優は自宅の門の前に立つと、また今度、と言って千種川に背を向ける。彼もまた、また今度、とだけ言うと、玄関の鍵を開ける優の後ろ姿を見守ること無く、肩で風を切って駅の方へと歩き出した。その足取りは、優の隣を歩いていたときよりも、随分早い足取りだった。寒さからではなく、元から早いのだと思わせるような、堂々とした足取りだった。