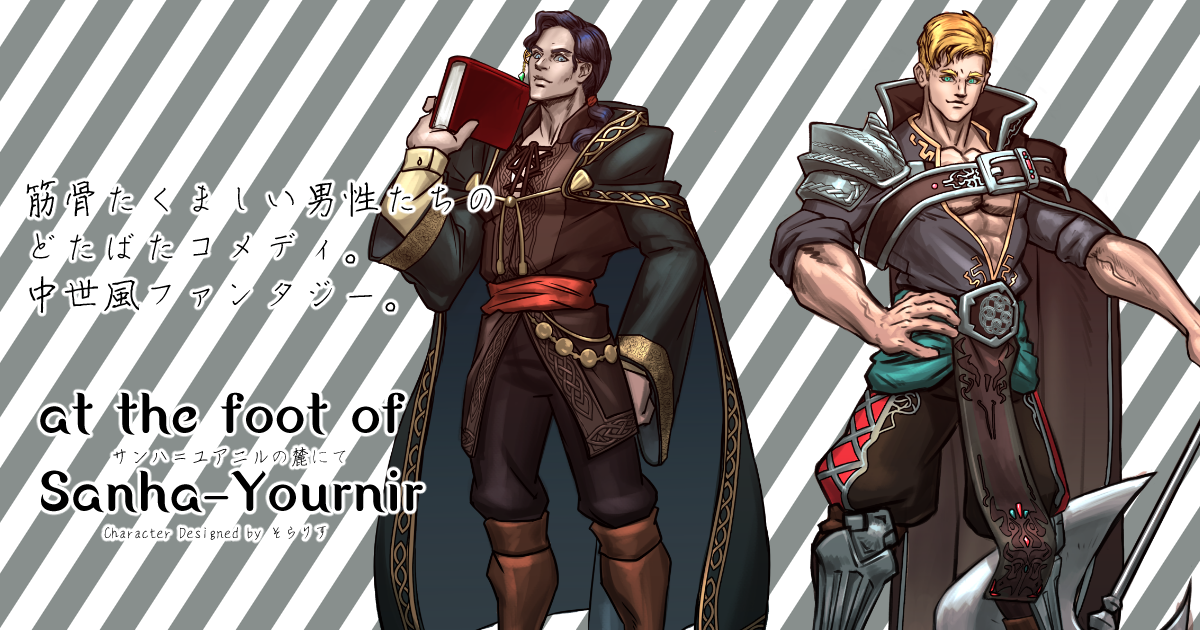「お、おはようございまーす……」
「おう、来たな。マクシミリアンなら、リビングにいるぜ」
「そうなんですね。わかりました」
「俺よりも切り方がうまいとよ」
誇っていいぞ。そう、にっ、と口の端を吊り上げて笑うヴォルフガングは、罠見てくる、と彼らの家をあとにする。そんな彼に苦笑しながら、メガネの位置を直しながら圭太はリビングに向かう。失礼します、と声をかけて入れば、そこには素材を箱から取り出して広げているマクシミリアンの姿があった。
「ん、来たな」
「来ました。実はちょっと楽しみで、早起きしました」
「そうか? ポーション作りは繊細さが求められるぞ。きちんと寝たんだろうな?」
「寝ましたよ! でも、透明化の薬品なんて、それこそファンタジーと言うか……向こうの世界じゃありえないっていうか……」
「そうなのか? まあ、こっちでも透明化の薬品はそれこそ悪用されるから、本当に販売が制限されるんだがな……」
「そりゃそうですよね……悪いことし放題だ……」
すこしばかりげっそりした様子の圭太に、そういうことだ、とマクシミリアンは神妙に頷く。だからこの透明化ポーションは一分限定なんですね、と圭太は二日前に拾ってきた素材をまじまじと見る。納品先は領主の元だと聞いたものだから、圭太はぎょっとした顔をする。だから金になるんだよな、と続けたマクシミリアンに、なるほどなあ……となんともいえない顔をする圭太。
これは下手に自分が手伝ったら、彼の商品に傷がつくのでは、と圭太は考える。それを素直に伝えるか少し悩んでから、隠し通すことでもないか、と圭太はマクシミリアンに自分が手伝っていいのかと尋ねる。不思議そうに首をひねっている彼に、自分が手伝って規定に合わなかったら問題ではないか、と事情をいえば、これ自体は作るのは誰でもできるんだよ、とマクシミリアンは笑う。
「素材だって、このあたりで自生していないものはあまりないしな。ドラゴンの鱗はたしかに竜とつながりがなければ手に入らないが、まあたまにメイナードの店でも取り扱っているしな。純水だって、水属性魔法が得意なやつの手を借りればいい。うちのポーション素材に使う純水はヴォルフガングの作ったものだしな」
「そうなんですね……」
「そのわりに流通されていないのは分かるか?」
「えーっと……精霊の相手が大変だから……?」
「そういうことだ。夜しか出てこないし、抜け殻をもらおうとすればいたずら三昧……それにな」
「それに?」
重要なことを言うように息を潜めたマクシミリアンに、圭太は思わず声を低くして問い直す。ごくり、と息を呑んで続きの言葉を待つと、いたずらに成功した子どものように彼は笑う。足跡が光るんだ、と。効果時間中ずっと足跡が光るし、めまいがするほど苦いから、よっぽどの事態でもなきゃ服用したいとは思わんよ、と笑う彼に、それはそうですね、と乾いた笑いを浮かべる圭太。
乾燥させてなお仄かに接着剤の原料ともなるエンチャントブルーピオニーと、光がゆっくり明滅している精霊の抜け殻ことウィッチウィスプをすり鉢にいれたマクシミリアンは、粉々になるまですりつぶしてくれ、と圭太に渡す。その間にマクシミリアンは友竜がくれた鱗を布で何重にもくるんで床に置く。
床においた布の塊の上から、鋼鉄製のハンマーを振り下ろす。がんがん、と何度も何度も振り下ろしていくマクシミリアン。この作業が一番面倒なんだよな、領主に売るにしても割に合わん、とぼやく彼に、どこでもドラゴンの鱗は硬いんだな、と圭太はかつてプレイしたRPGゲームを思い出す。あのゲームでは、ドラゴンの鱗なんてものはなかったが、グラフィックはいかにも硬そうな鱗だった。妹が読んでいるマンガでも、ドラゴンの鱗は硬いと書かれていた。
そんなに硬いんですか、と圭太が尋ねれば、これだけ叩いてこれだけしか削れないぐらいにはな、とマクシミリアンはため息を吐いて体を起こす。布でくるんだ鱗を取り出せば、ほとんど無傷だった。わずかに削れた鱗の粉を、エンチャントブルーピオニーとウィッチウィスプがすり潰されたすり鉢に流し込む。こんな少しでいいんですか、と圭太が尋ねれば、少しでいいんだ、とマクシミリアンは頷く。
「量が増えれば効果の持続性は高まるからな……」
「ああ、透明化が一分だけっていうのは……」
「そういうことだ。たまにどこぞの阿呆が鱗目当てに押しかけられたりするんだが……まあ、そういうこともあるな」
「ぶ、物騒ですね……」
「ま、街の外で暮らすっていうのは、中よりも物騒ではあるな」
はは、と笑うマクシミリアンに、長い前髪の向こうで遠い目をしてしまう圭太。その間に柔らかい材質の光る石・エルフィンストーンをすり鉢に入れるマクシミリアン。ごりごりと石を砕いて、すっかり混ざった粉だか粒だかわからないそれに、粘度の高いオリーブグリーンの液体――スターグローの樹液をマクシミリアンは匙一杯分入れる。ねっとりとした樹液の上から、ヴォルフガングに出させた純度が非常に高い水属性を帯びた水を流し込む。
「あとはサラサラになるまで混ぜたら終わりだ」
「これ、めちゃくちゃ粘ってますけど、本当にさらさらになるんですか!?」
「なるなる。最初は大変なんだが」
「ぎぎぎ……めっちゃ混ざらない……!」
えっちらおっちらと混ぜる圭太だったが、しばらく混ぜているうちに水と樹液が混ざり始める。重みが消え始めると、サラサラになるのはあっという間だった。みるみるうちにサラサラになり、透明な液体になったすり鉢の中身に、おお、と声を上げてしまう。初めてにしちゃあ上出来だな、と言いながらマクシミリアンは大瓶にすり鉢の中身を入れるために、漏斗を設置し、それに濾すための紙フィルターを乗せる。
紙フィルターで濾しながら大瓶を満たしていく液体を見ながら、圭太はこういうのって免許がいるんですか、と尋ねる。
「必要だな。医療錬金術師免許だな」
「えっ……それ、俺が手伝って本当に良かったんですか……!?」
「手伝うだけならな。混ぜるぐらいなら大丈夫なんだが、素材の乾燥は流石に俺がやらないといけないんだが。成分にも関わってくるしな」
「あ、そうなんですね……ならよかった……」
「錬金術師免許はあると、一気に仕事の幅が広がるんだが……いかんせん、読み書きがな。アカデミアにも行かないといけないから、金もかかるしな」
「こう考えると、異世界で生活するのって大変ですね……」
はあ、とため息をつく圭太に、マクシミリアンは帰ろうと思わないのか、と尋ねる。妹が多分嫌がるので、と圭太は苦笑する。俺も向こう側にあまり帰りたいと思わないのもあるんですが、と続ける。
「妹、学校であまり……その、いじめ……なんていうのか、集団で無視されたり、持ち物を捨てられたりしてて。うちは家族関係もあまりよくないから、向こうよりはこっちのほうが居心地がいいんですよね」
「そりゃ大変だな……無視はともかく、持ち物を捨てるのは犯罪だろうに」
「そうなんですよねえ……」
「ま、気が済むまでここにいればいいだろうよ」
瓶になみなみ湛えられた液体を確認し、紙フィルターに濾された残り滓だけがあるのを確認して、マクシミリアンはフィルターを錬金用ゴミ箱に捨てると、瓶の蓋をしっかりと締める。ちょうど蓋を締め終わったときに、ごんごん、とノッカーが叩かれる。
「領主の使いだな」
「わ、来るの早いですね」
「できたてを取りに来てくれ、って言っておいたからな。運ぶ間に成分が馴染んで、向こうで冷蔵保管されるころにはちょうどいい塩梅になるんだ」
「なるほど……ここでちょうどいい塩梅にして、冷蔵で運べないんですか?」
当然の疑問を圭太がぶつける。宅配便でクール便があるのだから、魔法のあるこの世界なら容易ではないか、と考えてのことだ。できなくはないんだが、とマクシミリアンは難しい顔をする。
引き取りに来た領主の使いに大瓶を渡して、代金を受取る。扉をしめて、施錠しながらマクシミリアンは冷蔵運送は魔力の消費が激しいんだ、と告げる。
「冷蔵用に限らないが基本的に触媒は、基本的に固定して使うものなんだ。魔導アイスボックスみたいにな。そうでないと安定しない。馬車にくくりつけるとなると、振動が伝わって均一に冷やせなくてな。そうなると氷結属性魔法をずっと使うことになる。ここから領主の家までそれなりにあってな……」
「なるほど……ずっと使うのは大変ですしね……」
「触媒が不安定な場所でも安定して使えたら、冷蔵で運ぶこともできるようになるんだろうけれどな」
まだしばらくは夢物語だろうな、と肩をすくめたマクシミリアンだったが、そういえばと口を開く。隣国トメラ・チズルメルでは触媒の移動コンテナでの安定化実験が進められていたな、と思い出す。山の向こうに住む文通相手が、そんなことを最近送られてきた手紙に書いていたのだ。
わりと近い未来でできそうな技術ですね、と圭太が笑えば、まだ失敗が続いているらしいけどな、とマクシミリアンは肩をすくめるのだった。