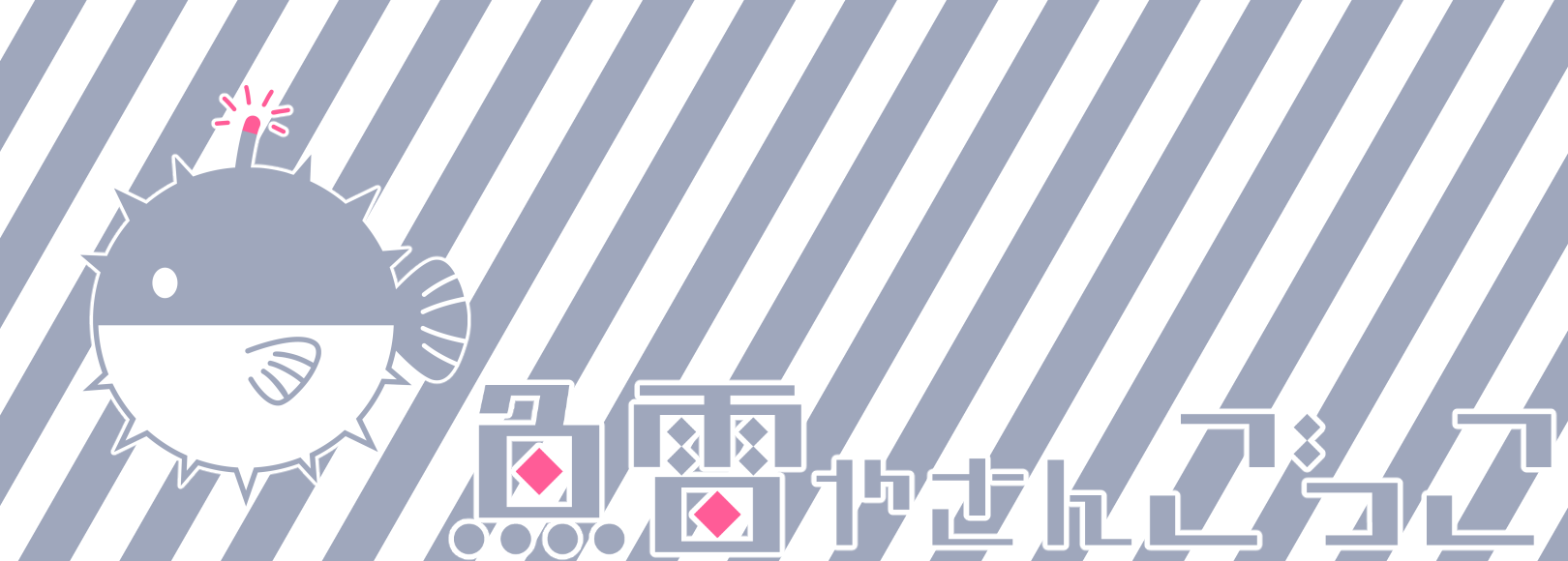栫井優(かこい・ゆう)はとかく派手な見た目をしている。男の平均身長はあるだろう高い背に日焼けした肌、アッシュグレイの髪には青いメッシュが入っている。ブレザーの制服はいつだって第三ボタンまで開けられていて、豊満な乳房が露出している。
スカートも短く折り畳まれ、肉付きのいい太ももがとてもよく見えている。安産型の大きな臀部も、スカート越しによく見える。
驚くべきは、豊満な乳房もたっぷりとした尻も、ただ雑に肉がついているだけではなく、完璧な脂肪と筋肉の配置により、だらしなさよりも美しさが先にくる。そして次に来るのは性欲だ。
正直な話、彼女の肢体でヌいたことがない男子生徒はこのクラスには、いやこの学校にはいないだろう。それほど、彼女の身体は魅力的だ。話すときに目線が豊かな北半球たちにいかないようにするのが精一杯だ。
平日に学校に行くのが別の意味で楽しみな自分としては、彼女の姿を見ることが出来ない休日は好きではない。そりゃあ、趣味はあるけれど、それとこれとは別なのだ。学校のマドンナを毎日拝める同じクラスというそれに慣れてしまい、趣味に打ち込めないのだ。
そんなこんなで、家でぐうたらと過ごしていると、母親に家中掃除するからしばらく出かけていろと家から追い出される。しかたなしに都心部まで出ようと、家の近くのバス停に向かう。ちょうど都合良く来たバスに乗り込み、都心部に向かう。ゆらゆら揺られて終点で降りると、見覚えのあるきれいなアッシュグレイの頭髪が見える。人違いかな、と思いながら人混みに流されながらよく見ると、青いメッシュが入っている。
栫井さんだ。そう思って近寄ろうとして、彼女がきょろきょろと左右を見渡している。誰か、人を待っているのだろうか。ちょうど、ここは待ち合わせにちょうどいい場所だしな。そう思って付かず離れずの距離で見ていると、ぬっと自分の進行方向からやたら背の高い男性がやってくる。
長身痩躯で、見てくれはぎょっとするほど美しい。容姿端麗、明眸皓歯(めいぼうこうし)。女性に使う言葉らしいが、羞花閉月(しゅうかへいげつ)も似合いそうな男だった。十人が、いや百人が彼を美しいというのではないかと思わせるほどの顔立ちだった。なんというか、どんな美醜に関する価値観を持っていても、よっぽどひねくれ曲がって、一般的な醜さを美しさだという人間でもない限り、彼を美しいと言わざるを得ないだろう。
しかし、遠目からでもなんというか――男は人間らしさが欠けているなと感じてしまう。なんというのか、美しく、完璧に整っている顔立ちからか、等身大の人形のように見えるのだ。その顔に表情が乗っていないせいもあるかもしれないが。
のっぺりしてるけど、とんでもない美丈夫だな、と思っていると、その男はずんずんと人波をかき分けてこちらに来る。人波をかき分けるというよりも、人が彼の美しさに恐れてどいているようにも見える。男はずんずんとこちらに近寄ってきたと思うと、ぴたりと足を止める。ちょうど栫井さんの手前で足を止める。
見おろすように栫井さんを見ている彼に、お前は彼女の何なんだ、と言いたい気持ちを抑える。だって、それは、自分こそ彼女の何なのかが分からないから、そこを突っ込まれたらたまったものじゃないからだ。
とはいえ、自分が沈黙して見守っていると、やほ、と栫井さんはけだるそうに目の前に立つ男に手を振る。あれだけの美女なんだから、年上の男と付き合いぐらいあっても仕方ないだろう。そう思いながら見守り続ける。
「マサキ、早いじゃん」
「はい。以前、きみを待たせてしまったから、調整したので」
「……待たされた事なんてあったっけ?」
「はい。先週、きみを五分待たせました。約束の時間より、きみは五分早く来る人間だと知らなかったため起きました。なので、今回は修正しました」
「あんね、人間、あんたみたいに時間ぴったりに現れることは難しいんだよ。だから、あたし、五分早く着くようにしてるだけ。だから、気にしなくていーの」
「いえ、よくはありません。きみの貴重な五分を無駄にしてしまったのは事実ですから」
「だから、全然あたしの五分とか貴重じゃないし。気にしなくていいっつの」
「いえ、よくはありません。きみは、とても貴重な発言をしてくれるので、大変参考になっています」
「……ああ、もう。なんでもいいよ」
「理解していただけていないようなので――」
「だぁから、もういいって。ほら、それより行くよ」
「理解を放棄したのですか? きみほどの人間がぼくの説明を理解出来ないとは到底――」
「はいはい。あとで聞くから、あんた、ちょっと黙ってて」
「黙れ、と言う指示は具体的に――」
なんというか、ぽかんとした。
美青年から発された台詞に圧倒された。なんというか、ちょっと人間らしさを感じないと思っていたけれど、ここまでか、という感じだ。まるで機械のような言葉に、ちょっと薄気味悪さを覚えたけれど、栫井さんはそんなことなど気にしていなくて――彼女のことも、ちょっと分からなかった。
薄気味悪い男に動じない女。それだけでなんというか、あの二人に対して忌避感を覚える。栫井さんを見かけた時点で、自分はそっとその場を立ち去るべきだったのだろう。自分の中の、学校のマドンナという虚像を砕かれないためには。
少し、気味が悪い。胸の辺りがもやもやとして、口の中が乾いて苦さを覚える。胃の奥がちくちくしてきて――とりあえず、何も考えたくなくて、気を紛らわせるために近くのコンビニに入ることにした。今は、この気持ち悪さを解決したくて、なんでもいいから炭酸飲料が飲みたかった。