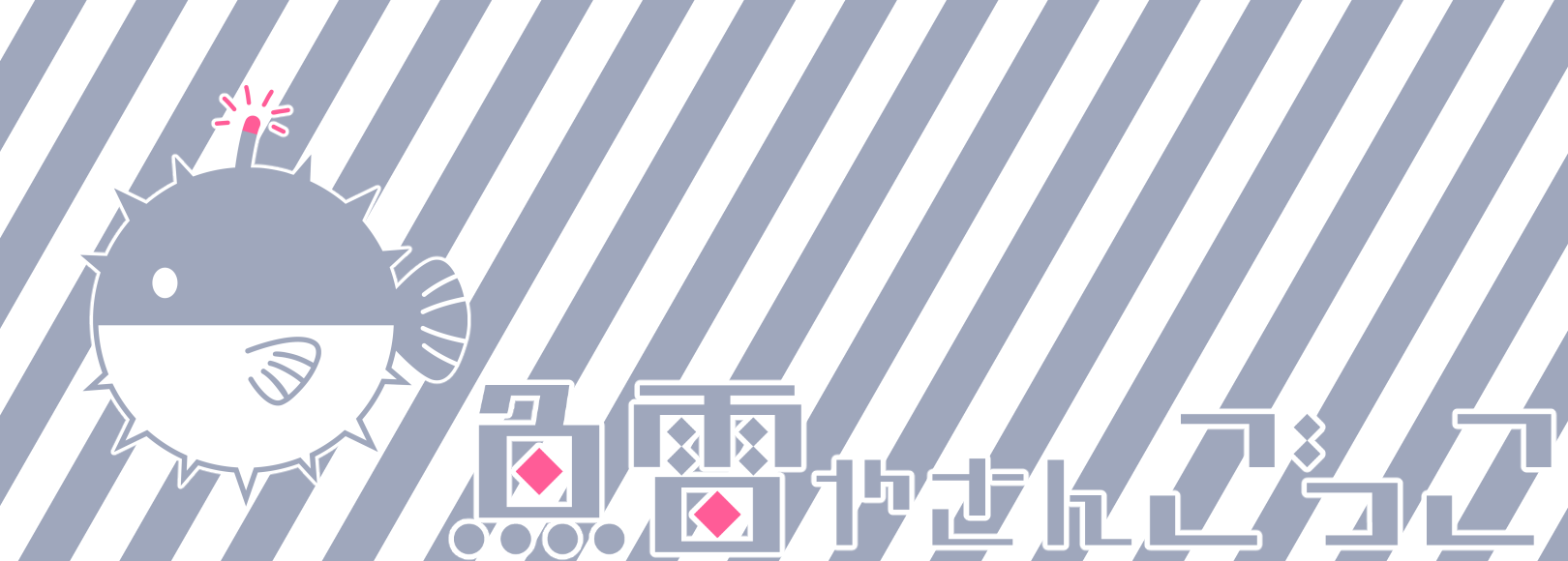「月食だって、今度の……いつだっけ」
「二十六日ですね。二十時十一分ごろから十五分程度と聞いています」
「へー。見れる時間、それだけなんだ」
「はい。そのようです」
じゅずずずず。
シアトル系コーヒーショップの季節限定フラペチーノを啜りながら、優は興味なさそうにへえ、という。
ソイラテをちびちびと飲んでいる千種川とクリームを啜る優の二人は、賑やかな店内に置いても浮いていた。
それも仕方がないことなのかもしれない。誰もが――よほど捻くれ曲がった美醜観を持っていなければ、誰しもが振り返る美男子と、成人向け漫画キャラクターが立体になったような、抜群のプロポーションの女性が二人並んでいるのだ。どうしたって目を引いてしまう。
ちらちらと好奇の視線を浴びながら、それすらも気にすることはなく、二人は会話を続けている。
「あれって、なんの影だっけ。地球?」
「はい。地球の影に月が入ることで欠けていきます。今回の月食では、十八時四十五分ごろから影に入るとされています」
「へー。そっから昇る月がどんどん影に入るから、満月が欠けていくってこと?」
「はい。そして月全体が影に入り、皆既食となるのが先述した時間になります」
「ああ、八時の」
「はい。赤みを帯びた満月はその時間しか見られません。しかし、日食と違い、月食は月が観測できる地域であれば、海外であっても同時刻に見られます。ロマンを感じますね」
「へー、面白いね。でも、あんた、真面目な話、ロマンとかわかんの?」
「いえ。この場合はそのように言うべきだと予想したまでです」
「だと思った」
空になったフラペチーノの容器から手を離し、優は、はー、とため息を吐く。月食に興味はありませんでしたか、と千種川は首を傾げる。
「父と母、そして姉たちは興味深そうにしておりましたので、優もそうだと思ったのですが」
「あー、まあ普通は興味あるんじゃない? ていうか、珍しくあんたから普通の話題がきたと思ったら、そういうことか。あたしが興味あると思ったから、振ったんだ」
「はい。会話は興味のあるものから始めるものだと学びましたので」
「えらーい。頭打ってぶっとんだわりに、そういうところは学習能力高いよね。やっぱ、最高学府行ってるからかね」
「そこに因果関係があるかは分かりませんので、ぼくからいう言葉はありません」
「別にいーよ。興味あるわけじゃないし」
思い切り伸びをした優は、月食にまるで興味がないわけじゃないよ、と返す。そんな彼女に、さらに首を傾げる千種川。
他人より興味の度合いが薄い、ということでしょうか。そう尋ねた彼に、そんなところ、とだけ返す。
「別に、実際に見たら多分、おー、ってなるんじゃないかな」
「なるほど。心揺さぶられる、ということですね」
「たぶんね。でも、それだけを楽しみに一日は過ごせないってだけ」
「なるほど。他に興味を引くものがある、ということでしょうか?」
「え? あー……どうなんだろ。興味を引くものは……別にないけど」
そこで口をつぐんだ彼女に、千種川はないのですか、という。彼からすれば、興味を引くものがないのに、世の中が興奮するものに興奮しないことに違和感を覚えていることだろう。
難しいなあ、と言って優は唇を尖らせる。んー、と悩んでいた彼女だったが、ああ、と口を開く。
「まわりが興奮すると、逆に冷めるんだよね」
「なるほど。周囲が興奮状態であるがゆえに、優は冷静になる、と」
「だからって、集団行動ができないわけじゃないけどね。あたしが、あーおもしろーって思った範囲では楽しむし、興味だってあるよ。まあ、なんていうか興奮する人が他にいるなら、見やすい位置を譲る……っていうのかな」
言葉にするの難しいね、とにやりと笑った優。難しいのですね、とオウム返しする千種川に、そうだよ、と興味なさげに返した優は席から立ち上がる。
「帰りますか?」
「んー。服見たいんだよね。あんたもくる?」
「荷物持ち、ということでしょうか」
「そんなとこ。まあ、あんたがいると変に話しかけられないし、楽なんだよね」
「なるほど。そういう利点もあるのですね」
「そゆこと。で、くるの?」
「はい。ついていきます」
二人は席から立ち上がると、ゴミ箱に空になった容器を捨てる。そのまま店を後にして、近くのエスカレーターで二つ上のアパレルショップの並ぶ階に向かうのだった。