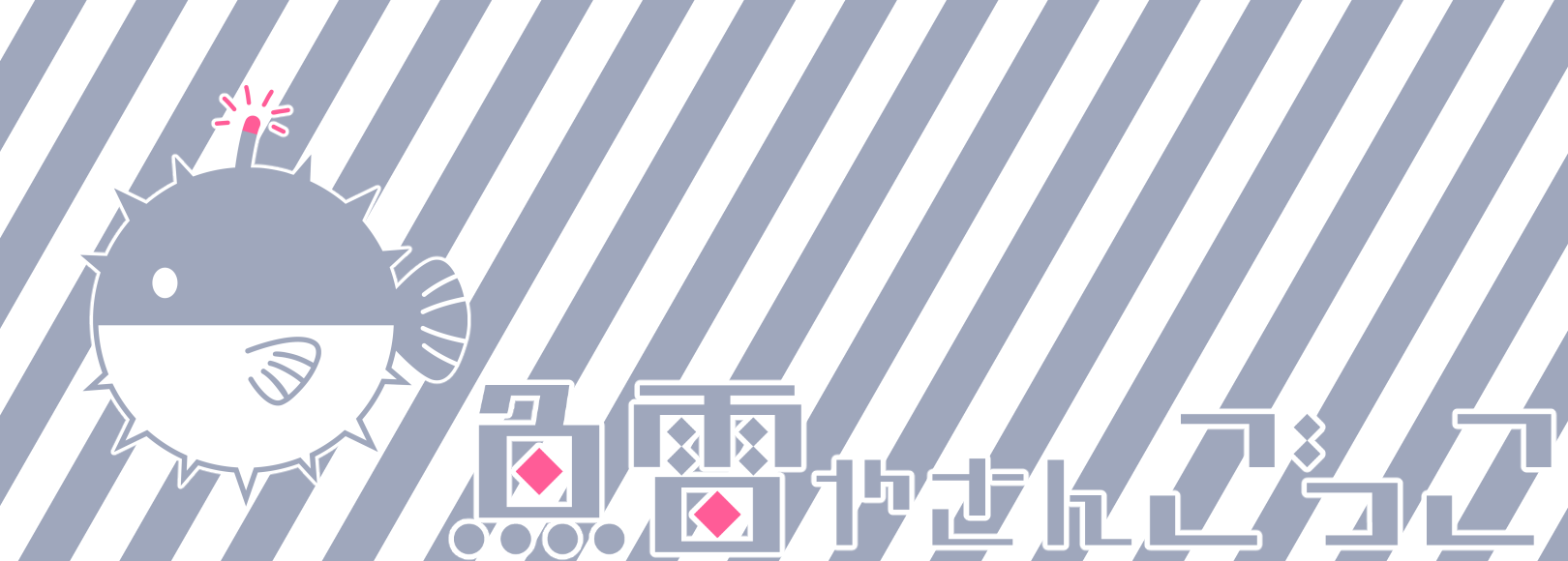千種川雅貴(ちくさがわ・まさき)という男は異様なまでに顔がいい。
紫がかった黒い髪は短く切り揃えられ、綺麗な天使の輪がかかっている。黒いまつ毛は女子も羨むほどに長く、シャープペンの芯だって――もしかしたら、ボールペンの芯だって余裕で乗る長さだ。
モデルかよと突っ込みたくなるほど小さい顔に、バランスよく配置された顔のパーツ。人の顔は左右非対称なんて言うが、この男の場合はそれが最小限らしい。いや、むしろないのかもしれない。完璧なまでに左右対称であるように見える。
赤い舌に吸い込まれるような黒い目。最近ハマっているゲームのステータスでいうなら最高数値をたたき出していることだろう。眉目秀麗というのはこの男のための言葉なんだろうな。
唯一残念なのは、表情が削げ落ちていることだけで――ただ、ここに表情まで乗っていたら吸い寄せられて潰れていそうなので、乗っていなくてよかったのかもしれない。
なんでも、大学入試直後に大怪我を負い、それまでの記憶を全て吹っ飛ばしたとかなんとかで――それまでの彼を知る者からすれば、全くの別人らしい。だが、話を聞くに顔を活かして女を食い散らかしていたらしいので、今のほうが人間味はないがまともで好感が持てるらしい。
まあ、目の前にいる男についてつらつらと述べてみたりしたものだが、まあつまらないのだ。ようは暇を潰したかったのである、俺は。
講義が終わって、女どもはちらちらと千種川を見ている。どうやら、あわよくば昼飯を一緒にとか考えているのだろう。
面倒くさいことに、女子は女子で協定があるらしい。まあ、男子も男子で美人を取り合う野蛮な、血で血を流すことをする前に手を取り合う協定があるから、きっとそんなものなんだろう。
誰一人として彼に声をかけないでいるのは、彼を独り占めしない、という暗黙のルールがあるかららしい。彼から話しかけられたら別らしいが――人目があるところでは、自分からモーションをかけないのがルールらしい。
変な空気が流れる中、千種川はある女に声をかける。少し派手な見た目な女で、それが意外だった。
こいつ、派手な女が好みなのか、と思っていると、女の耳元に手を伸ばす。ぬっ、と何も言わずに伸ばされた手に、女はときめきながら千種川くん、と甘ったるい声をあげる。周りの女の目が痛い。なんで俺の目の前の席に座っている女に声をかけたんだ。
「このイヤリング」
「え?」
「どちらで購入されたのですか?」
「えっ、えっと……駅のビルに入ってる、アクセサリーショップ……」
「どちらの駅ですか?」
「えっと……たしか……」
女は大学から四駅ほど離れた駅名を言う。千種川はなるほど、というと女の耳元から手を離す。そのままカバンを引っ掴むと、すたすたと教室を後にする。
女はぽかーんとしている。どうやら、用事は女がつけているイヤリングだったらしい。ちら、と見れば大きなフープのついたイヤリングをしている。そんなものが趣味なのか、と思っていると、千種川くん誰かにプレゼントするのかな、と女の友達らしい別の派手女が口を開く。
「えっ、誰に!? あたしに!?」
「あんたなわけないでしょ。他の女じゃない?」
「えー? そうかな……ああ、でも千種川くん、街で見る時待ち合わせしてるっぽい、って聞いたことある」
「待ち合わせ? 誰とよ」
「なんか、すごい派手な女って聞いた」
「千種川くんに派手な女は釣り合い取れなくない?」
「わかるわー」
お前らがそれを言うんかい。
思わず脳内で突っ込んでしまう。げっそりしながら女たちの詮ない噂話を聞きたくなくて、そそくさと俺も教室を後にする。
昼飯何にしようと思いながら廊下を歩いていると、千種川が廊下の端でスマートフォンをいじっている。
あ、こいつのスマホ、俺と同じ機種だ――と思っていると、その画面が目に入る。どうやら、さっきの派手な女の言っていた駅の周辺を検索しているらしい。
これは本当に誰かにプレゼントをするのかね、なんて思って、俺は千種川、と声をかける。
ぐるりと顔を向けたやつは、そのまま体を俺に向ける。どうかしましたか、と話しかけてくる声は温度なんてなくて触れたら凍りつきそうだ。
「いや、悪い。画面が見えてさ。誰かになんか、贈るのか?」
「……なぜ贈り物をすると思ったのですか?」
「え? ああ、さっき話し声が聞こえててさ。女もんのイヤリングなんて、誰かに贈るのかなって考えるのが普通だろ?」
お前がつけるとは考えにくいからさ。
そう答えると、なるほど、と千種川は何かを理解したように頷く。一般的に男性は女性向けのアクセサリーはつけませんね、と確認するように自問自答している。
そんな彼に誰に贈るんだよ、と尋ねてみる。思いがけない答えが返ってきても、そうでなくても面白そうなのでアリだ。そう思っての質問に、彼は小首を傾げてからふむ、と言う。
「友人に贈ろうと思いまして」
「へえ。誕生日が近いのか?」
「いえ、違います。そもそも、優の誕生日を知りませんね。なるほど、贈り物は日頃の感謝の気持ちさえあればいつでもいいのだと思っていましたが、誕生日に贈るものでしたか」
「あ!? ああー……あー……い、いや、なんでもない日に贈ったっていいと思うぞ!? ただ、なんか……そう! 渡す理由が付けやすい日に普通は贈るもんだからさ、びっくりした」
「……? 驚くようなことでしょうか?」
「まあ……普通は照れくさいし、あんまりやらねーなあ」
「なるほど。しないほうがいいのでしょうか」
「いや、別にしちゃいけないわけじゃねえし……贈りたいなら贈ってやったほうが、多分そいつも喜ぶんじゃねえの?」
しどろもどろになりつつも、千種川にそう伝える。なんというか、突拍子もないが、きっとこいつなりにその優という女性には助けられているのだろう。――それこそ、贈り物をしたいと思う程度には。
不思議そうな顔をしていた千種川だったが、納得したのか、俺の意見を聞き入れなくてもいいと判断したのか、スマートフォンに目を落とす。その画面には女性向けのアクセサリーショップが映し出されており、スクロールされたページには開店時間と閉店時間が書かれている。四限まで講義を受けても、余裕で間に合う時間だ。
きっとおそらく確実に――その店に行くのだろう。時間と場所を口ずさむと千種川は画面を閉じる。
「では、失礼します」
「お、おう」
ぺこりと一礼して千種川は廊下を進む。丁字路を左に曲がると、そのひょろっとした背の高い姿は見えなくなる。
改めて話すのは二度目だが、やはり変なやつだなと思う。なんというか――実は人間ではない何かがその身体の中にいると言われても、多分俺は信じると思う。
そんなことを考えながら、俺は食堂へと足を向けた。こうしている間に、人気の日替わり定食は売り切れてしまっているかもしれないのだ。