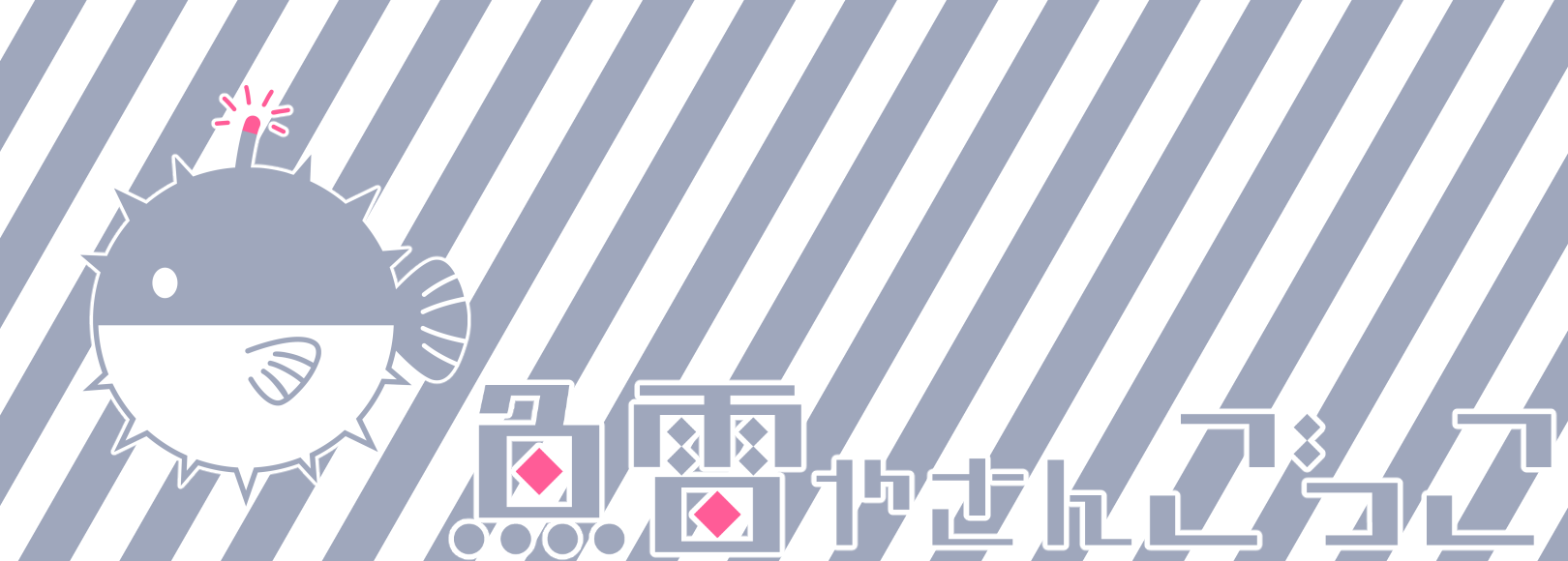ぽってりした唇はつん、と尖らせる必要すらないほど女性的だ。垂れ目だとはいえ、女性にしては精悍な顔立ちの中で、そこだけは嫌に肉感的だ。ふっくらとした唇は、むしゃぶりつきたくなる。
窓に薄く反射する彼女の肉感的な体に、店の外にいる男も、店の中にいる男もちらちらと見てしまう。それは仕方がないことだ。それほどまでに彼女の身体は肉感的なのだから。もはや、現代のリリスかもしれないと向かいに座る芸術家の友人は感嘆のため息を吐いている。
「お前なあ」
「だって、見ろよ。完璧な身体と思わないか?」
「完璧ってな……」
「あの胸の形。ただ大きいだけじゃない。重力に負けてない」
「そら、下着つけてるからだろ……」
「あの尻の大きさだって、ただでかいだけじゃない。上を向いているし、垂れてない。若さだけじゃないぞ、あれは」
「ああ、はいはい……」
「ありゃあ、現代のリリスだな。エロスにもな、下品と上品があるんだが、あの体つきは完璧だよ。黄金比だな、あれは」
最高だな。
そういう顔はやに下がっていて、なんというか……それっぽいことを言っているだけで、単にこいつは彼女をそういう目で見ているだけなのではないか、と思ってしまう。呆れた、と言っても過言ではない。顔を見れば、まだ若いのが分かる。見た目こそ――成熟したその身体は成人していてもおかしくはないが、その顔立ちはまだあどけなさを残していて、未成年だろうことを示している。未成年にたいしてなにを考えているんだか……呆れながら、コーヒーをすする。苦い。いつもより苦く感じるのは、前に座る男のせいだろう。
俺たちがそんなたわいのない下卑た話をしている間も、彼女は開けっぱなしだったカバンのファスナーを閉じるぐらいで、あとはずっとスマートフォンを触っている。なんというか、いたってどこにでもいる、ありふれた少女だ。見た目こそ、成人女性ですら持ち得てない肉体だけれども。
目を逸らして適当に相槌を打つ。悪いやつではないから、と思いつつも、今後はちょっと距離をおこうかな、と考える。
ぽってりしたその唇がストローを咥える。アイスティーをすする彼女のもとに、一人の男性が近寄る。これがまた、とんでもない美形だった。
左右対称になるよう配置されたパーツ。目は切長で少し釣り上がっている。薄い唇がに、すっと通った鼻筋。ひょろりと細長い身体は、まあ今時な感じだ。筋肉はあまりないように見える。向かいに座る少女が肉肉しいからだろうか、その対比にくらくらしてしまいそうだ。
「待たせましたか」
「そこまで? てか、珍しくない? マサキが遅いとか」
「電車が人身事故を起こしまして。連絡をしたはずですが、既読が付かなかったのを知っています」
「え、マジ。ごめん、マンガ見てたから、ラインの通知見てなかったわ」
「いえ、気にしていません。ただ無為に過ごさせたわけではないのなら」
「ふーん……ま、いいや」
なんてことはない……いや、なんか違和感があるやりとりだ。連れは恋人がいるのかよ、とぶつぶつ不貞腐れているが、これはきっと、そんなのではない気がする。恋人というか……もっと遠いような気がする。例えるなら、ただの茶飲み仲間くらいの距離ではないだろうか。
そんなことを考えながら、最後のポテトをつまむ。空になった紙の容器を潰して、行こうぜ、と言われる。おう、と返しながら、トレイを片付けて紙ゴミを捨てる。
「やっぱり、良い女はもう手をつけられてるよなー」
「そりゃそうだろ」
「くそー。なんで俺には良い女が寄ってこないんだ?」
「そりゃ……お前、自分の職業考えてみろよ。胡散臭いだろ」
「そうかぁ? アーティストって言えばかっこいいだろ!」
「はいはい……」
「あ、てめー!」
いつものやりとりをしながら、ちらと窓越しに店内を見る。反射したガラスで、中の様子はよく見えなかった。