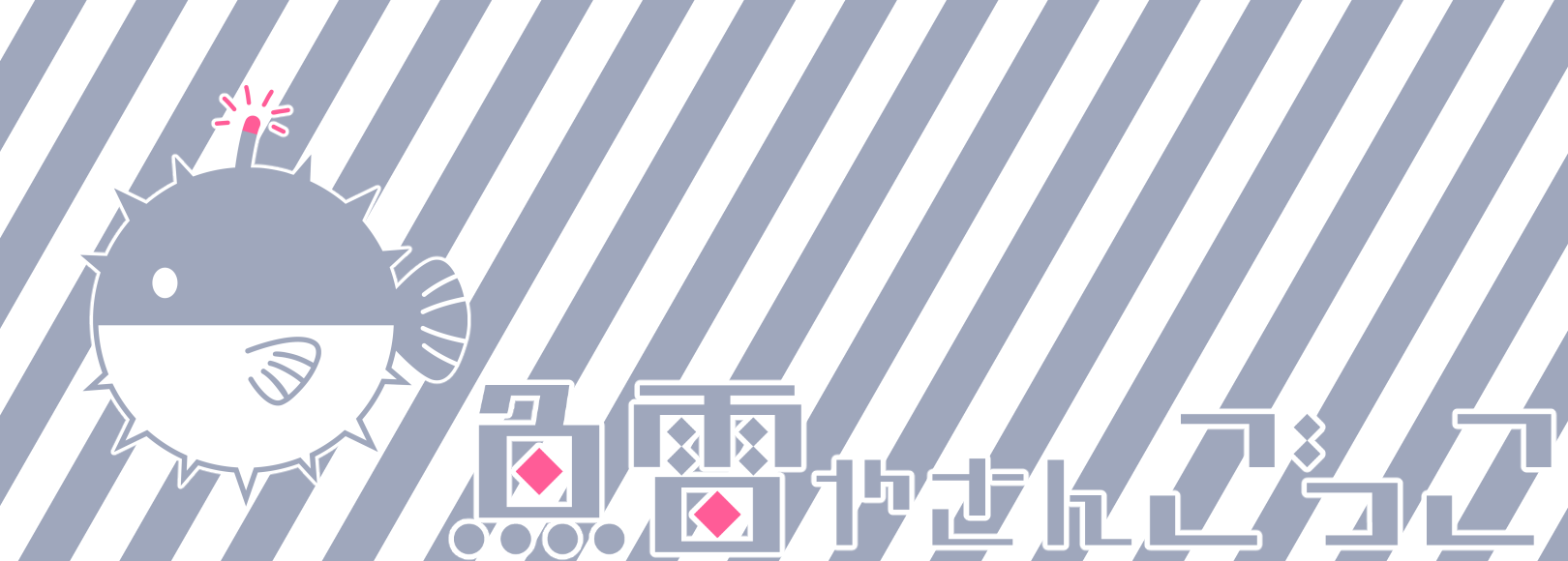イスに腰を下ろして話しかけてくる千種川。クイーンサイズのベッドにあぐらをかいて座った優は、あー……と声を出すと、がしがしと頭をかく。考えがまとまらないと言わんばかりの様子の彼女を、ただ千種川はじっと見つめている。まとまるまで待つつもりのようだ。あぐらをかいていた足をほどいて、もう一度ベッドに転がった優は、ばたばたと脚を動かしてうなる。むっちりとした太ももとふくらはぎが、ばたばたとした動きに合わせて揺れる。
しばらくばたばたしていた彼女だったが、疲れたのか飽きたのか、動きを止めて身体を起こす。その間ずっとイスに座って瞬きしかしなかった千種川は、優の顔をじっと見ていた。
「えーっと……ようは、地球以外に人間よりも頭がいい文明があるって聞いて、あたしがどう思ったかってこと?」
「ええ。どう思いましたか?」
「んー……まあ、そりゃ銀河の外ならあるんじゃないの?」
「ふむ。では、質問を変えましょう。地球……範囲を広げましょう。天の川銀河の外にある非常に高度に発展した文明。そこから見れば、天の川銀河における文明はあまりにも稚拙で、取るに足らない文明であると言われたら、どう感じますか?」
強い否定の言葉で質問を繰り返す千種川。その目には、相変わらず感情は何もない。その目を見返しながら、優は口を開く。おそらく、彼は何かを確認しようとしているのだろう。そして、それはこれまでの二人の関係性を崩すものなのだろう。そう、確信をしながら。
「……でも、それって、その文明から見れば事実なんでしょ? じゃあ、しょうがなくない?」
「ふむ。しょうがない、ですか。それは諦めからですか?」
「んあー……あたしは、そうだな。諦めもあるけど、受け入れ、かな」
「受け入れ、ですか」
「そ。諦めて、事実を受け入れることで、その先が見える――たとえば、銀河の向こうの文明が持ってる技術だったり、知識だったりとかさ。そういうのが手に入るんじゃないかなって」
「なるほど。抵抗せずに受け入れることで、先行する文明から何らかの助力が得られる可能性がある、と」
「ん、そんなとこ。ほら、変に抵抗したら、そういうのがなくなるかもしれないでしょ」
まあ、明確な侵略行為なら抵抗しないといけないんだろうけどさ。
そう笑った彼女に、こてんと首をかしげて千種川は、目をパチパチと瞬かせる。賢明な判断ですね、と言う。そうかな、と返す彼女に、この質問において侵略行為を前提ではないと認識したことが素晴らしい、と褒める。
「ん? だって、言わなかったじゃん。攻め入るなんて。攻め入るんだったら、あんたは絶対それを言うじゃん。そうじゃないんだなって思ったんだけど……あれ、これ侵略戦争が元だった?」
「いえ、そういうわけではありません。そうですね、シチュエーションについて話していなかったのは問題です。訂正しましょう。会談の場において、否定されたということにしましょうか」
「ああ……でも、それでもあたしの考えは変わらないかな。非難されたから激高したって、どうしようもなくない? 相手のほうが強い武器とか持ってるかも知れないんだしさ。まあ、実際にそうなったとき、受け入れられるかは分かんないけどさ」
「なるほど。実際に直面したときにその対応が出来るかどうかは不明であっても、話の上ではそのように解釈する、ということですね」
「ん、そう。だって、はなっから喧嘩は売られてないんでしょ? そいつらからしたら、ただ事実を指摘してるだけなんだしさ」
だったら、まず向こうの技術力を見せてもらってから、平和的に対応したいよねー。
そう話す彼女に、千種川は目をゆるりと細める。目を細めて、彼はなるほど、と小さくこぼす。あなたは賢明な判断をしますね、と。
「そうかな。ただの逃げかもよ。自分で何かを決定したくないから、それっぽいことを言って他人に決定権を押しつけてるのかも」
「それは他人と意見をすりあわせ、より合理的な意見を得ることに繋がる可能性があります。やはり、あなたは得がたい人物だ」
「……なに、急に褒めだして」
「いえ、あなたになら話しても問題ないだろうと判断しました。これはぼく単独の判断であり、彼らへの承認はとっておりません。ですが、今の会話データログを提供すれば、彼らも納得するでしょう」
何を言っているんだこいつ、と言わんばかりに胡乱げな目を千種川に向ける優。その視線など気にもせずに、うんうんと頷く彼はボストンバッグを開ける。優のバッグを間借りして、彼は持ち込んだノートパソコンに何かを打ち込む。かたかたとキーボードを指先も見えぬ速さで叩いて居たかと思えば、何か、USBメモリのように見えるものを読み込ませている。何かを読み込ませていた彼は、パソコンを閉じるとこちらに向き直る。
イスのそばに置かれたテーブルに投げ出されていた千種川のスマートフォンは、彼がUSBメモリらしきものを読み込んでいる間から、ひっきりなしに鳴っている。それを無視して話し出そうとする彼に、電話ぐらいとってやりなよ、と優は指摘する。それに頭を振って、彼はスマートフォンの電源を落とす。
「いいの? しんないよ、あとで凄い量の着歴残ってても」
「ええ、かまいません。ぼくの独断専行に対する苦情ですから」
「いや……それは聞いてあげなよ……」
「あとで処理できる些末ごとです。ですが、あなたにこの話をできる場所を探すのは少々骨が折れるものですから、なるべくなら一度で済ませたいのです」
「ああ……そう? まあ、別にあたしに関係ないから、別に好きにすれば良いんじゃない……?」
それで話したい事って何、と優は先を促す。こくりと頷いて千種川は口を開く。珍しく、彼の声に温度が感じられた。普段は温かくも冷たくもない、機械的な声色の彼なのに珍しい。そう彼女が思っていると、彼は少し首をかしげて切り出した。
「察していると思いますが、ぼくたちは人ではありません。いえ、正しくいうならば──地球人ではない、と言うべきでしょう」