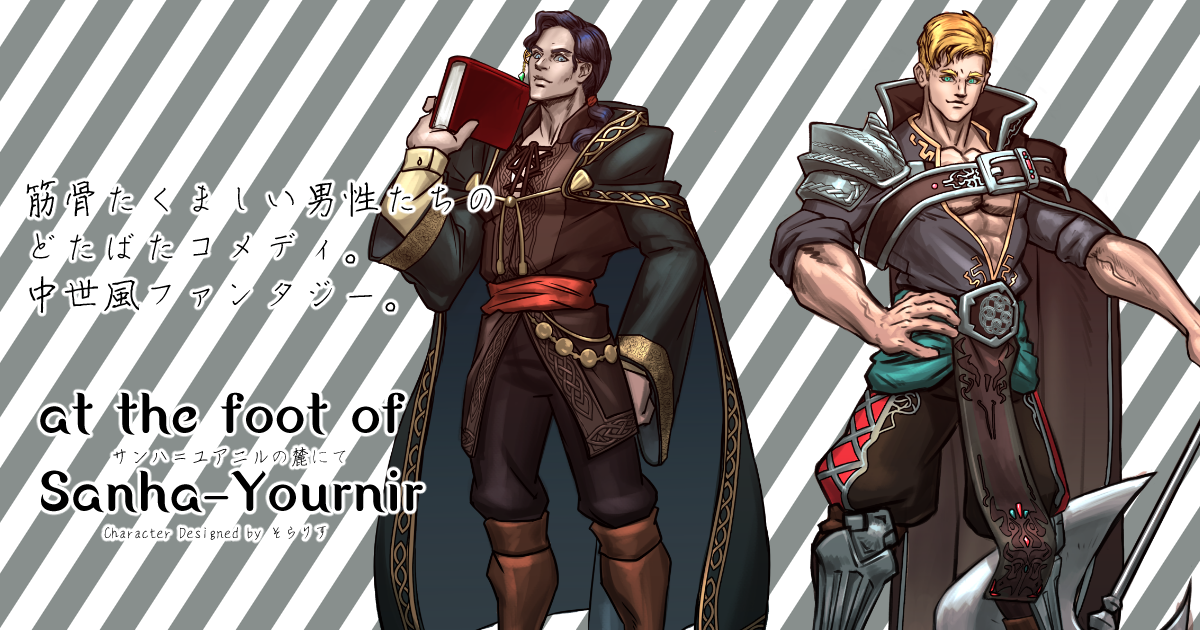マクシミリアン=イルデブランドは鍋を火にかけていた。
特に友人であるドルノ族たちの特有の言語、竜語(ドルンノード)で綴られた書籍の翻訳依頼があるわけでもなければ、製本の依頼があるわけでもない。至って平々凡々平和な日々だ。
季節は冬に入ろうとしていた。サンハ=ユアニルはただでさえ冷涼な気候のサンク・キタテウェルトの中でも山の麓にある街であるからか、冬に入るのも早い。短い夏の間に生産されたトマトたちを、大量にざく切りにしすりつぶす。それを鍋で煮詰めるのだ。刻むのもすり潰し器にかけるのも、量があればなかなか疲れるものである。規格外に大柄で人並みよりも体力のあるマクシミリアンであってもだ。
マクシミリアンの巨躯に合わせた手回し式のすり潰し器で、ごりごりと山積みにしたトマトの赤い果実を荒くすり潰す。鍋にいっぱいになるまですり潰したところ冒頭に戻る。たまねぎの巨大な塊をみじん切りにして鍋に放り込む。取り寄せた大量の海塩もいれて、ふつふつと火にかける。
「ここからが時間に任せるしかないんだよな……焦げないように気をつけながら……と」
鍋底が焦げないように木ベラをゆっくりと動かして、底からしっかりとかき混ぜる。じっくりと煮詰める時間は長い。鍋いっぱいのすり潰しトマトとみじん切りたまねぎが半分になるまで煮詰めるのだから。
じっくりことこと煮詰め続けて、流石に木ベラを動かす腕が疲れてきたマクシミリアンは逆の手で木ベラを動かす。火を使っているから離れられず、かといって木べらを回す以外で出来ることも特にない。うーん、とたまに首を回して気を紛らわせるが、それでもしっかりと底からかき混ぜ続ける。そうでなければ、すぐに焦げ付いてしまうのだ。
時計の短針がひとつ歩を進めると、玄関のドアががちゃがちゃを音を立てる。鍵を開けて入ってきたのは同居人のヴォルフガングだ。いつだったか彼が拾ってきた琥珀色の毛並みを持つ三つ首の幼犬・ラギウスを散歩させてきたのだ。頭が三つもあるからか、右にいきたい、左にいきたい、と中々賑やかなようだが、拾ってきたヴォルフガングがしっかりと面倒を見ていることが友人たちの間では意外らしい。マクシミリアンとしては、存外真面目なところもある彼のことだから意外でもなんでもないのだが。
マクシミアンはおかえり、と言いながら玄関を見ることなく鍋をかき混ぜ続ける。外の手洗い場で足を洗ってきたラギウスを床に下ろしたヴォルフガングは、もうそんな季節か、とのそのそとマクシミリアンの手元をちらと見てリビングのソファーに腰を下ろす。
「もう冬になるからな。先に作っておかないとだろ」
「季節巡るの早いよなあ。ちょっと前まで夏だったのにな」
「まったくだな」
「てことは、ラギウスもそろそろ換毛期にはいるのか?」
「あー……そうだな」
「……てことは、ブラッシングしてやるか。なあ、マクシミリアン」
「知らんぞ」
「まだ何も言ってねえだろ! どこにあるのか、探すの手伝えってだけだ!」
「言ってるだろ!」
一カ所にまとめておいただろ、ラギウスの道具は。
鍋をかき混ぜながら、マクシミリアンはどこに片付けたのかは知らないけどな、と言いながら教えてやる。そういや全部一緒にしたな、と彼の指摘で思い出したらしいヴォルフガングは棚を下から上まで探し始める。
その様子をちら、と見ながらマクシミリアンはこの煮詰める作業が終わって、煮沸消毒した瓶に詰める作業が終わったら手伝わされるんだろうな、と見え透いた未来のことを理解してしまってため息を吐く。
そんなマクシミリアンの心情など露知らないラギウスの幼犬は、へっへっ、と舌を出しながら部屋を駆け回っているのだけれども。